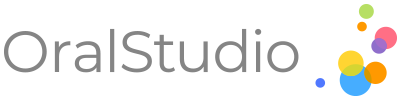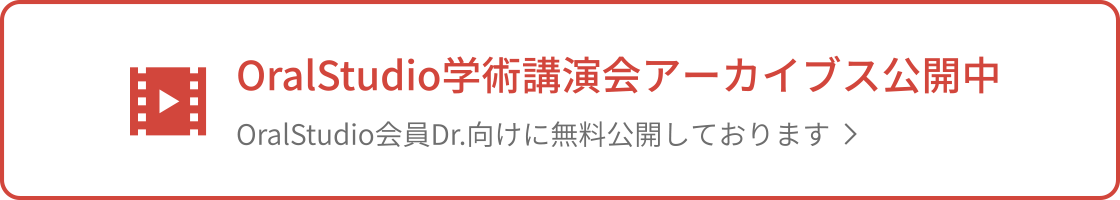味覚試験
ミカクシケン
-
分野名
-
解説
-
【種類】
味覚試験には、「電気味覚試験」「濾紙ディスク試験」「血液検査による微量金属の定量試験」等がある。
【電気味覚試験】
定量的な障害部位の検査が可能
【濾紙ディスク試験】
半定量的検査である。
基本的な4種の味、甘味(砂糖)、酸味(レモン汁)、塩味(食塩)、苦味(アスピリン、キニーネ、アロエなど)をろ紙にしみこませて舌面上にあてて行う。
濃度の調整された試験味質を用い、低濃度から高濃度へ移し、味らしきものを感じた濃度を検知閾値とし、味の性質を正確に感知したところを認知閾値とする。
【血液検査】
微量金属の定量を行う。
【心因性味覚障害】
心理テストも必要である。
【口腔乾燥や感染症による味覚異常】
疑われる場合には、これらの検査も必要となり、まれではあるが、篩板の近くの腫瘍、膿瘍、骨折など器質的異常の検査のため、頭部CT検査やMRI検査が必要な場合もある。
★★★ ぜひご活用ください! ★★★
OralStudio歯科辞書はリンクフリー。
ぜひ当辞書のリンクをご活用ください。
「出典:OralStudio歯科辞書」とご記載頂けますと幸いです。